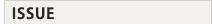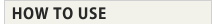展開図、構造図、設備図を確認しよう

構造材をあえて剥き出しにした天井が美しい。建築家・片岡英和さんの作品事例「神戸山手台の家/ローコスト狭小住宅」。
前編では「平面詳細図」「矩計図(かなばかりず)」の解説をいたしましたが、後編では、展開図、構造図、設備図について解説いたします。前編に引き続き、建築家・片岡英和さんが実際に作られた「実施設計図書」を用いて解説をいたします。
展開図を確認しよう
部屋ごとに兵器麺を一面ずつ内部から見た図で、各室の立面的な見え方を表現します。窓の高さや、手摺の取付き高さ、造作家具の見え方など、室内の形状や仕上げのチェックに欠かせない図です。通常1/30もしくは1/50の縮尺で描かれます。

ウォークインクローゼットと寝室を展開した、展開図の一部です。展開図は、スイッチやコンセントなどの位置、持ち込み家具や電化製品の設置場所の確認、カウンターやキャビネットの高さがあっているかなどをチェックします。展開図(かなばかりず)を拡大して見る
構造図を確認しよう
伏図、軸組図、詳細図の3つに分類されます。こちらは伏図。構造図では基礎の形状や金具・筋かいの入り方を確認します。伏図、軸組図、詳細図の3つに分類され、1/100の縮尺で作成されています。

構造計算(風圧力、地震力など)により、柱や梁の部材寸法を決定されています。また、建物の融資条件や保険料に耐震等級が唱われている場合がありますので、耐震に関して事前に建築家に相談しておきましょう。構造図を拡大して見る
設備図を確認しよう
電気関係の図面と給排水設備の図面がそれぞれ作成されます。こちらは電気関係の図面です。取付位置の確認はもちろん、器具表の品番チェックも行いましょう。

設備スペック、スイッチやコンセントの位置、照明器具の種別などが図面化されています。コンセントの位置等は図面から読み取れるのですが、照明器具や便器、洗面器等はどの様なものが使われているか、食い違いが生じないよう、あらためて写真等でビジュアル的な確認をしておいた方が良いでしょう。設備図(電気設備図)を拡大して見る